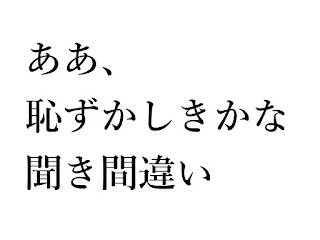こんばんは!
めぐぺ。です。
みなさんは、英語の聞き間違いをした経験はありますか?
あるとしたら、どんな単語でしたか?
今日もいつものようにブログのネタを考えていたら、ふと昔やっていた英語の聞き間違いのことを思い出しました。はずかしーい(*´д`*)記憶ですが、今回はそちらを紹介します。
英語を話す時、日本人は並べた単語をひとつずつ言いがちですが、ネイティブの人達は繋げて言うので、いくつかの単語もまとまってひとつに聞こえたりすることありますよね?実際それが、私が英語ってカッコイイなーと思った理由のひとつでもあります。
参考までに、私が英語について好きだなーと感じるところは、
・いくつかの単語が繋がって聴こえる(音が変わる)
・英語独特のリズム感(抑揚)
・世界中の人達といろんな話ができる
・日本語ではない別の世界に行ける
などありますが、
日本語では言葉で伝えにくいことも、英語でだと言える。なんて、普段の自分とは違う人間になれるような感覚になることがありました。
人の悪口が平気で言えちゃう!とかではありませんが、日本語だとなかなか言えずにいたイエスかノーかの回答も、英語だとはっきり言えたりしたんです。また、意見を述べるのも、日本語よりも英語の方が自信を持って言えました。不思議ですよね。
そんな風に、個人的にもいろんな感覚で捉えていた英語。必死で勉強をしていた当時、完全に聞き間違いをしていたのに、本人はいたって大真面目で全く気づいていなかった言い回し。
それが何かというと、
First of all
です。
まず第一に、という意味ですね。「・・・したのには、◯◯個の理由があります。まず第一に、〜。二つ目は〜。三つ目は、、、。」という感じで使います。
これを何と聞き間違えていたかというと、
Festival
です。
日本人的には、それぞれ、First of all ファースト・オブ・オール とFestival フェスティバルですが、ネイティブが発音すると、どちらもファストヴォルのように似たような音に聞こえます。
今でこそわかりますが、当時はまだFirst of all の使い方も、ネイティブがどのように発音するのかもわからず。全く見当違いのところでFestivalが出てきたように感じて、なんでかな〜と思った記憶がうっすら残っていますが、聞いた当初は自分が聞いたものがFirst of allとは結びつきませんでした(笑)
この経験があったので、いつかカッコよくFirst of allを使ってやろう!と思っていたのですが、後に転職する時の面接でその時がやって来ました。この時私がこの言い回しを使ったことは印象的だったようで、後から「感心した」と言っていただきましたが、使った本人は目標達成で勝手に満足していました。
このFirst of all とFestivalの聞き間違い。後で聞いたら他の人も「聞き間違っていた」と言っていたので、おそらく同じ間違いをしていた人は多いのではないでしょうか。でも、
恥ずかしいことではありません。
今知っている自分からすると、過去の失敗は恥ずかしいことになるのかもしれませんが、知ってしまえば単純な話でも、知らないのだから仕方がない。この発音を間違えたからと言って、誰かをひどく傷つけることもありません。
私としては、間違ったおかげでそれぞれが実際はどう発音されるのかがわかったので、貴重な経験だったと思っています。こういう実戦で間違って、そこから学ぶことや感じることが昔の英語の授業ではあまりなかったなぁ、と思いました。
授業で当てられて答えられない時や、間違ったことを言ってしまった時の恥ずかしさ。そもそも授業で当てられるかもしれない恐怖を毎回感じながら、授業を受けていました。
特に高校時代。音読は好きだったのですが、読み出すと人前でも自分の世界に入ってしまうので、なるべく本気で読まないようにしていました。今なら、「間違っていいんだよー」「それが大事なんだよー」と大手を振って言ってあげられるのに。でも、逆にそれがなければ今の自分にはなっていなかったのかも知れません。未来は今に、今は未来に繋がっているんですね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、私が過去にしていた英語の聞き間違いについて紹介しました。みなさんも何か聞き間違いをしていて、後で何のことかがわかって面白かったなんて経験はありませんか?でも、どうぞそう言った経験は大切にしてくださいね。むしろ楽しむくらいでいいのかもしれません。
シェアしたいのがある!という方は、ぜひコメント欄やtwitterで教えてくださいね。